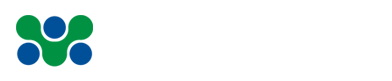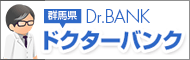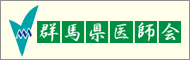| 日時: | 令和元年7月8日(月)12:20~12:40 |
|---|---|
| ゲスト: | 群馬大学医学部附属病院麻酔科蘇生科 三森亮太先生、群馬大学医学部附属病院脳神経内科 星野礼央和先生、群馬大学医学部附属病院初期臨床研修医2年目 清水一輝先生 |
| 参加者: | 登坂さん(5)、永井さん(5)、梶原さん(4)、佐藤さん(4)、増田さん(4)、 宮下さん(4)、森さん(4)、小林さん(3)、今井さん(2)、石塚さん(1)、 岩崎さん(1)、太田さん(1)、上村さん(1)、田胡さん(1)、松村さん(1) *( )内は学年 群馬県健康福祉部医務課医師確保対策室 杉山医師確保対策係長 群馬県地域医療支援センター専任医師 羽鳥 |


センター医師
今日は、すごい参加者の人数ですね。地域枠卒業の先生方も、お忙しい中ご協力いただきましてありがとうございます。北毛地域と西毛地域の先生方の臨床研修を伺います。
清水先生
卒後2年目です。臨床研修は群馬大学医学部附属病院の「たすき掛け」で、1年目はA病院、2年目は群馬大学医学部附属病院で研修しています。そろそろ診療科を決めないといけないと思っています。
三森先生
卒後4年目です。臨床研修はA病院で2年間でした。臨床研修も、病院によって、診療や雰囲気に違いがあるから選択に悩むよね。自分は大学5年生のポリクリ後に臨床研修先について考え始めました。
清水先生
自分も同じです。選択ポリクリで病院を絞り込みました。病院見学はあまり行かなかったです。自分で手続きしなくても病院を見学できるセンターのセミナーを活用した方がよいです。
三森先生
通常の病院見学は、自分で病院に連絡したり、手続きが大変です。臨床研修の2年間のプログラムは、ガチガチに組まれているものや、自由度が高かったりするものなど、病院によって特徴があります。研修が、希望する診療科に影響することもあります。研修先を考える際には、ある程度、希望する診療科を見据えて選択できると良いですよ。
清水先生
たすき掛けなら、2年間のうちに複数の病院で研修できます。先のことが決まらないなら、たすき掛けを選択するという方法もあります。
在学生
先生の研修先の病院は、救急が忙しいというイメージが強いです。実際にはいかがでしたか。
星野先生
はい。相当数の患者さんが来院されます。でも、研修としては、多すぎず少なすぎず。様々な疾患を経験しました。その辺りの地域では、他に総合病院がないため、二次医療からそれより高次の医療まで求められることも大きいのかと思います。
在学生
A病院は雰囲気がとても良いとの評判を聞きますが、特にどこが良いのですか。
清水先生
医師間の雰囲気も良いけど、事務職の方がすごく親身にやってくれます。
三森先生
病院によって研修医室が「ある」・「ない」、ある場合、「どこにあるか」を見てみるのも良いですよ。研修医室があれば上司の目を気にせずリラックスできる反面、質問したい時などは、上司の部屋に入らないといけないので、ハードルが上がる。研修医室と上司の部屋が離れていても、敷居は高くなります。
清水先生
病院見学に行くときには、何か視点(テーマ)を持って見ると良いです。「雰囲気はいいか」、「設備はどうか」など。
三森先生
1つ上の先輩から教わることが多いので、その雰囲気が大事。1つ上の先輩の様子を見るためにも、6年生になってからも病院見学に行くと良いですよ。
在校生
先生が現在の脳神経内科に決めた経緯を教えてください。私も脳神経内科に興味があります。
星野先生
在学中の4年生頃からかな、まず学問的に興味を持ちました。学んでいるように、診断がつかない、わからない病気もありますが、研究のテーマにもなる得るということでもあり、診療と同じように学問的に奥が深い分野だと思います。
在校生
病院案内やホームページを見ると、スキーなど、診療外のサポートもあるようですが。
星野先生
アクティビティに対して助成が受けられます。でも、自分はインドア派だったので活用しませんでした。研修を支えてくださるスタッフも優しく、過ごしやすいと思いますよ。6年生は、卒試、国試と試験が続くよね。でも、皆と一緒に勉強していけば大丈夫だよ。頑張ってくださいね。
それぞれの自己紹介だけでも大いに盛り上がり、昼の休憩時間という短時間の中でしたが、研修医時代の様子について伺うことができました。参加学生の中には、目の前にロールモデルとなる医師の姿を確認した方もいたかもしれません。地域医療体験セミナーに参加していた地域枠学生が、在学中に多くのことを学び、地域の方々と多くの関わりを持ちながら社会人となって後輩たちに温かく言葉をかけている―入学当初から地域枠学生の成長を見守ってきたセンタースタッフにとっても何よりうれしいひと時でした。