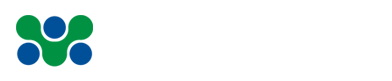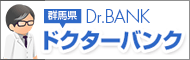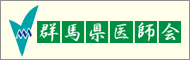| 日時: | 令和元年6月27日(木)/令和元年7月11日(木)12:20~12:40 |
|---|---|
| ゲスト: | 群馬大学医学部附属病院地域医療研究・教育センター 奥 裕子先生 |
| 参加者: | 群馬大学医学部医学科生 鈴木さん(4)、宮下さん(4)、森さん(4)、 河内さん(2)/青木さん(3)、森田さん(3)、西野さん(2) *( )内は学年 群馬県地域医療支援センター専任医師 羽鳥 |

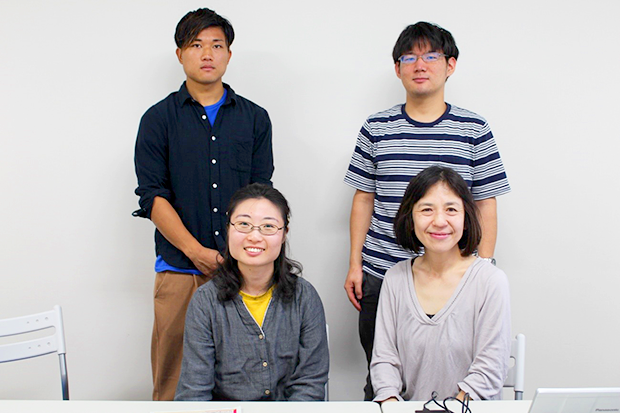
センター医師
専門医制度の中で、新たな診療科として総合診療科ができました。地域医療に関心の高い地域枠の皆さんにとって、直接先生とお話しできることは楽しみですよね。今日は、救命・総合医療センター総合診療部門で診療されている奥先生にお話を伺います。
奥先生
こんにちは。まず、スライドを使って、“総合診療科ってなぜ必要なの?”というところについてお話しします。今の医療はだいぶ臓器別に専門診療するようになっています。患者さんからすると、例えば、○○(手の痛み、胸のあたりの痛み、めまいなど)については、どこにかかればいいの?何科の先生がいいの?っていうことが起こりうるわけですが、これは大学病院でも日常茶飯事に起こることです。
プライマリ・ケアという言葉を耳にしたことがあると思いますが、簡単に言うと、“総合的に診る医療”ということになるかと思います。患者さんにとって、何でも診てくれる身近な医師は頼りになる存在ですよね。
プライマリ・ケアには5つの理念があります。
- 近接性には、『地理的』『経済的』『時間的』『精神的』
- 包括性には、『予防から治療、リハビリテーションまで』『全人的医療』『Common diseaseを中心とした全科的医療』『小児から老人まで』
- 協調性には、『専門医との密接な関係』『チーム・メンバーとの協調』『Patient request approach(住民との協調)』『社会的医療資源の活用』
- 継続性には、『ゆりかごから墓場まで』『病気の時も健康な時も』『病気の時は外来-病棟-外来へと継続的に』
- 責任性には、『医療内容の監査システム』『生涯教育』『患者への十分な説明』
(日本プライマリ・ケア連合学会ホームページより)
難しく書かれているように感じると思いますが、つまり、“最も近いところで”、“なんでも診ますよ”、“周りとも患者さんともいろいろ連携していますよ”、“赤ちゃんからお年寄りまで”、というような内容が含まれていますよね。
大学病院では、○○の症状で、どの診療科にかかったらよいのか分からない、他の医院や病院で検査したけれど原因が分からない、といった内容で相談を受けますし、教員として、教育や若手の指導、研究も行っています。
新しい専門医として、内科や外科と同じ位置づけに総合診療専門医ができました。現在は、大学内に総合診療専門研修プログラムがあり、専門医の取得を目指します。またサブスペシャルティ領域の専門医の取得もあることから、内科専門医とのダブルボード(2つ目以上の新専門医資格を取得すること)も可能となる方向で話が進んでいると聞いています。
在校生
総合診療というと、内科的な診療を行うのかなあというイメージがあります。
奥先生
内科的な診療ももちろんありますし、もともと私は循環器内科が専門だったので、そちらの専門診療をすることもあります。でも、簡単な応急処置などは、自分で行うこともあります。実際に、出張に行くような、より地域の病院では、傷口の手当てなどを日常診療で行います。大きな病院では、専門の医師にお願いすることが多いですが、外科的領域の研修も必要だと思いますよ。
在学生
診療の幅が広くて、どこまで学ぶのかが気になります。診断のほかに、専門診療もしますか?
奥先生
受診した患者さんを診断し、自分の専門性を活かして診療を継続することも多いです。例えば、甲状腺疾患のフォローでは、投薬の調節も含めて診療しますし、対応の難しい患者さんの診療なども、経験が必要となります。受診した患者さんとは別に、ご家族に関する相談を受けたり、家族全体の診療にかかわったりすることもありますよ。糖尿病とか高血圧とか。
何となくイメージしている総合診療医について、プライマリ・ケアにも興味があり、さらには専門診療も習得したい学生さんから、多くの質問が出ていました。Common diseaseからその奥の診断・治療の奥深さを知り、専門診療を身につけたところで改めて家庭医や総合医の役割を知る。ベテラン医師になっても多くの経験が増えても、前向きに患者さんと向き合い、新たなことを学ぶ向上心の必要性をお話ししているようにも感じられ、改めて地域医療の重要性について考える貴重な時間となりました。奥先生、ありがとうございました。